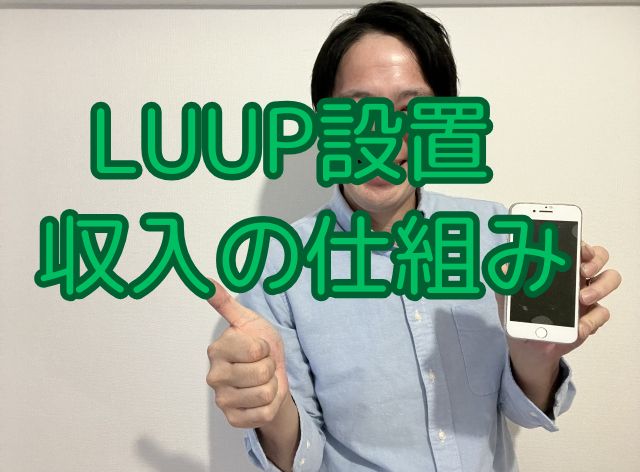難しいオタク用語を百個、多様なジャンルから厳選してご紹介します。アニメの制作現場で使われる専門的な言葉から、アイドルファンの間で交わされる隠語、ゲームのディープなスラングまで、これらを知っていればあなたも「通」の仲間入りです。
- SNSやイベントでの専門的な会話が理解できるようになる
- 作品やカルチャーをより深く味わえるようになる
- 同じ趣味を持つ仲間とのコミュニケーションが円滑になる
- オタク文化の多様性と奥深さを知り、視野が広がる
アニメ制作・作画用語 (1-25)
- アオリ (Aori)被写体を下から見上げる構図のこと。「煽り」と書く。遠近感を強調(パースを付ける)することで、キャラクターの巨大さや威圧感、力強さを表現するために用いられる。巨大ロボットの登場シーンや、対峙するキャラクターの権威性を示す場面で多用される。対義語は、上から見下ろす「俯瞰(ふかん)」。
- 板野サーカス (Itano Circus)アニメーター・板野一郎氏が確立した作画スタイルに由来する俗称。無数のミサイルが、デタラメなようでいて計算された軌道を描きながら画面内を飛び交う、超高速戦闘シーンを指す。圧倒的な情報量とスピード感で視聴者を魅了する、アニメーターの技術の結晶ともいえる高度な作画技術である。
- 入れパン (Irepann)一枚の長い背景画を用意し、その一部分だけを映した状態からカメラを動かして(パンして)別の部分を映す撮影技法。「PAN」はカメラを振る動きを指す。キャラクターが歩いている場面などで、背景だけが動いているように見せるために使われる。限られた素材で動きを表現するためのアニメならではの手法。
- AB作画 (Ē Bī Sakuga)AとB、2種類の絵(セル)を1コマずつ交互に表示させる作画技法。チカチカと点滅しているような効果や、キャラクターが変身する際のぐにゃりとした特殊な視覚効果を生み出す。主にエフェクト作画で用いられ、特に80年代のロボットアニメやバトルアニメで特徴的な表現として多用された。
- オン撮 (On-satsu)「本番撮影」の略語。原画、動画、背景、彩色されたセルなど、作画の全工程を終えた素材をひとつの映像として合成する最終工程を指す。かつては物理的なフィルムで撮影していた名残の言葉だが、デジタル制作が主流の現代でも、コンポジット作業全般を指して「撮影」という言葉が使われている。
- 返し (Kaeshi)作画したキャラクターやメカなどの素材を、左右反転させて再利用すること。作画の手間を省くためのテクニックだが、キャラクターが身につけているアクセサリーや文字などが反転してしまうミスも起こりやすい。特に急ぎの制作現場で用いられることがある、アニメ制作の裏側が垣間見える用語でもある。
- 口パク (Kuchi-paku)キャラクターが話すセリフに合わせて、口の形を「あ」「い」「う」などの母音を基本としたパターンで作画し、動かすこと。通常は3コマ(1秒に8枚の絵)で描かれることが多い。声優の演技と口の動きが一致していると、キャラクターが本当に話しているかのような生命感が生まれる重要な作業。
- 作監 (Sakkan)「作画監督」の略称。多数のアニメーターが描いた原画の絵柄を統一し、クオリティを担保する重要な役職。キャラクターの表情や動き、デザインに矛盾がないかを確認し、必要であれば修正(作監修)を入れる。作品の絵柄の良し悪しは作画監督の腕前に大きく左右されるため、ファンからも注目される。
- T.U/T.B (Track Up/Track Back)カメラ自体が被写体に物理的に近づいていく(Track Up)、または遠ざかっていく(Track Back)撮影技法のこと。ズームイン/アウトがレンズの焦点距離を変えるのに対し、T.U/T.Bはカメラの位置を動かすため、背景と被写体の間の遠近感がよりダイナミックに変化する。緊迫したシーンなどで多用される。
- 動撮 (Dōsatsu)「動画撮影」の略語。彩色前の、線画で描かれた動画の段階で一度撮影し、動きに問題がないかチェックする工程。この段階でタイミングや動きの滑らかさを確認し、問題があれば修正を行う。リテイクの手間を減らし、制作の効率を上げるために行われる中間作業。アナログ時代からの名残の言葉。
- トレス (Trace)元の絵の上に紙を置き、下の線をなぞって描き写す行為。アニメ制作では、ラフな原画を綺麗な線に整える「クリンナップ」の際や、複雑な模様などを正確に描くために行われる。また、実写映像を元に動きをなぞる「ロトスコープ」もトレスの一種。デジタル作画の普及で作業は容易になった。
- 中割り (Nakawari)原画と原画の間の動きを描く「動画」を作成する作業のこと。例えば「パンチを振りかぶった絵」と「パンチが当たりきった絵」という2枚の原画の間に、腕の軌道を描いた動画を複数枚挟むことで、動きが滑らかに見えるようになる。アニメの滑らかさは、この中割りの枚数と質に大きく依存する。
- 二値化 (Nichika)画像を白と黒の2色のみで構成されたデータに変換すること。アニメ制作では、紙に描かれた線画をスキャンしてPCに取り込む際に、鉛筆の濃淡などをなくし、はっきりとした線データ(ラスターデータ)にするために行われる。この後、ペイントソフトで色を塗る「彩色」の工程に移る。
- バラシ (Barashi)撮影が完了した後、重ねていたセル画を一枚一枚分解していく作業のこと。セル画は高価で再利用することもあったため、次のシーンで使うセルを管理する上で重要な工程だった。デジタル制作が主流の現代では、レイヤー分けされたデータを管理することを指す場合もある。アナログ時代の名残が強い言葉。
- 引き (Hiki)カメラが被写体から遠ざかるように撮影し、画面に映る範囲を広げていくカメラワーク。キャラクターのいる場所の全体像を見せたり、キャラクターの孤独感を演出したりする際に使われる。対義語は、被写体にどんどん寄っていく「寄り(Yori)」。状況説明や心情描写に欠かせない基本的な演出手法。
- BOOK (Bukku)背景と複数のセル(キャラクターやエフェクトなど)を一つのセットとして扱う際の単位。例えば、キャラクターA、キャラクターB、爆発のエフェクト、背景、という4つのレイヤーを重ねて1つのカットを構成する場合、これを「1BOOK」と数える。複雑なカットではBOOKの枚数が多くなる。
- BG (Bī Jī)”Background”の略語で、背景画そのものや、背景美術を担当する役職を指す言葉。BGのクオリティは作品の世界観や雰囲気を大きく左右する。キャラクターの絵(セル)とは別の工程で、専門の美術スタッフによって描かれることが多い。単に「背景」と言うよりも業界用語らしい響きがある。
- フルコマ (Furu-koma)アニメーションを1秒あたり24枚、すべてのコマに違う絵を割り当てて制作する贅沢な手法。「フルアニメーション」とも言う。動きが非常に滑らかになるが、膨大な作画枚数が必要になるため、劇場作品の決めシーンや、特に動きを見せたい短時間のカットで限定的に使われることが多い。
- Vコン (Bui-kon)「ビデオコンテ」の略。作品の設計図である「絵コンテ」をコマごとに撮影し、仮のセリフやBGM、効果音などを入れて映像化したもの。制作の初期段階で、作品全体の流れや演出の意図、各シーンの尺(時間)などを関係者間で共有するための重要な資料となる。
- 目パチ (Me-pachi)キャラクターの「まばたき」のアニメーションのこと。通常は「開いた目」「半分閉じた目」「閉じた目」の3枚の絵で構成される。キャラクターが生きている感じ(生き生き感)を出すための基本的な動作であり、セリフの合間や驚いた時など、感情表現の補助としても重要な役割を担っている。
- フォロー (Forō)歩いたり走ったりしている移動中の被写体を、カメラが同じ速度で追いかけてフレーム内に収め続ける撮影技法。「追っかけ」とも言う。背景が流れていくことで、キャラクターの移動速度を効果的に表現できる。アクションシーンや日常の歩行シーンなど、様々な場面で使われる基本的なカメラワーク。
- 密着マルチ (Mitchaku Maruchi)「密着マルチプレーン」の略。キャラクターなどの手前に置いた背景(BG)素材と、奥に置いたBG素材を、それぞれ異なる速度でスライドさせることで、カメラが回り込んでいるかのような立体感や奥行きを生み出す撮影技法。特にアナログ時代には高度な技術と手間を要した、職人技の一つ。
- イキウチ (Ikiuchi)「生き打ち」と書き、キャラクターに生命感を与えるための細かな動きを指す。セリフを話していない時でも、肩が微かに上下する呼吸の芝居(肩で息をする動き)や、髪の毛が風で揺れる様子などを加えることで、キャラクターがその場で本当に存在しているかのような実在感を演出する手法。
- ウス (Usu)動画を描く(中割りする)際に、下の絵(原画など)を透かして見るために使われる薄い紙のこと。「薄紙」が語源。アニメーターが使うタップという穴開け器で穴をあけ、作画机のタップに固定して使用する。これにより、紙がズレることなく正確な線を引くことができる。デジタル化以前の必須道具。
- ペーパー撮 (Pēpā-satsu)彩色を施す前の、鉛筆で描かれた線画の状態(ペーパー)のまま一度撮影して動きを確認すること。「線撮(せんさつ)」とも言う。この段階で動きのタイミングや滑らかさを監督や演出がチェックする。問題があればこの時点で修正するため、後の工程での手戻りを防ぐ重要な役割を持つ。

漫画・同人・印刷用語 (26-40)
- 赤ブー (Akabū)同人誌即売会を主催する企業「AKABOO INTER NATIONAL」の通称。主に女性向けのオールジャンルイベント「COMIC CITY」などを全国で手掛けている。ロゴマークが赤いブタであることからこの愛称で親しまれており、同人活動をしている人にとっては非常に馴染み深い存在である。
- 遊び紙 (Asobigami)本の表紙と本文の間に入れられる、装飾目的の紙のこと。色や質感の異なる特殊紙を使うことで、本の装丁に高級感や個性を持たせることができる。同人誌では、作品の世界観を表現したり、特別感を演出したりするために、作者のこだわりとして付け加えられることが多い。
- 自家通販 (Jikatsūhan)同人サークルが、書店などの委託販売サービスを利用せず、自分たちで直接、作品の注文受付から梱包、発送までを行う販売方法。手数料がかからないメリットがあるが、個人情報の管理や発送作業など、すべての手間を自分たちで負う必要がある。サークル主の負担は大きいが、ファンとの距離は近い。
- 写植 (Shashoku)元々は「写真植字」の略で、写真の技術を応用して文字を印画紙に焼き付け、版下を作成する方法。漫画制作においては、フキダシの中にセリフの文字を配置する作業全般を指す。現在はPCのDTPソフトで行うのが主流だが、フォントの種類や文字の配置は、漫画の読みやすさを左右する重要な要素。
- 背幅 (Sebaba)本の背表紙の厚みのこと。同人誌を印刷所に発注する際、ページ数と使用する紙の種類によって背幅を計算し、それに合わせて背表紙のデザインデータを作成する必要がある。背幅の計算を間違えると、文字が側面にずれたり、デザインが崩れたりするため、入稿前の重要な確認事項の一つ。
- 断ち切り (Tachikiri)印刷後に製本する際、仕上げに本の端を裁断(断裁)する。その時に切り落とされる領域を含めて、絵や背景を仕上がりサイズよりも外側まで描いておくこと、またその領域を指す。「塗り足し」とも言う。これをしないと、裁断が少しズレた際に紙の地の色(白)が出てしまうため、必須の作業。
- 丁合 (Chōai)印刷された大量のページを、1ページ目から最終ページまで正しい順序に揃え、一冊の本の形にまとめる製本工程のこと。手作業や機械で行われる。この工程でページの順番を間違えると「乱丁」、ページが抜けてしまうと「落丁」という印刷ミス(印刷事故)につながる。
- 虎の穴 (Tora no Ana)同人誌や漫画、キャラクターグッズなどを専門に扱う大手小売店。通称「とら」。全国に店舗を展開するほか、オンラインでの同人誌委託販売サービスも行っており、多くの同人サークルが作品を頒布する際の主要な販路となっている。オタク文化を支えるインフラの一つと言える存在。
- ドブ (Dobu)本を見開いたときの、左右のページが綴じられている中央の谷間の部分。この領域は非常に見えにくくなるため、重要な絵やセリフがドブにかからないようにレイアウトを組む必要がある。特に見開きで一枚の絵を描く際には、ドブでキャラクターの顔が分断されないよう細心の注意が払われる。
- 入稿 (Nyūkō)完成した漫画やイラストの原稿データを、印刷所に提出(アップロード)すること。印刷所が定めた締切日までに入稿を完了させないと、希望するイベントでの頒布に間に合わなくなる。多くの作家が締切直前まで作業に追われるため、入稿は同人活動における一つのクライマックスでもある。
- ノンブル (Nonburu)フランス語の “nombre”(数字)に由来し、本のページ番号を指す印刷用語。読者の読みやすさはもちろん、印刷・製本時の丁合(ページの順序を揃える作業)ミスを防ぐためにも不可欠。デザインの一部として、ノンブルのフォントや配置にこだわる作家も多い。
- 表1, 表4 (Hyō-ichi, Hyō-yon)本の表紙まわりを指す印刷用語。「表1」は表紙、「表2」は表紙の裏、「表3」は裏表紙の裏、「表4」は裏表紙のこと。同人誌の入稿データを作成する際、これらの区別は必須の知識となる。特に表2・表3に印刷(表2・3印刷)をすると、より凝った装丁の本を作ることができる。
- 袋とじ (Fukurotoji)製本の際にページを二つ折りにし、折り目のない小口(開く側)を綴じ、袋状にする製本方法。読者は中身を読むためにペーパーナイフなどで袋を開ける必要がある。雑誌の袋とじはアダルトな内容が多いが、同人誌では、おまけ漫画やあとがきなど、特別なコンテンツを収録する演出として使われる。
- モアレ (Moare)フランス語の “moiré” に由来。規則正しい模様(ドットの集合体であるスクリーントーンなど)を重ね合わせた際に、もとの模様にはない周期的な縞模様が発生する現象。意図しないモアレの発生は作画ミスと見なされるため、特にデジタルでトーンを扱う際には、角度や線数の設定に注意が必要。
- 級数 (Kyūsū)写植やDTPで使われる、文字の大きさを示す単位。1級は0.25mmに相当する。一般的に使われる「ポイント(pt)」とは異なる、日本の印刷業界で古くから使われてきた単位系である。漫画のセリフの文字サイズを指定する際などに、今でも専門的な場面で使われることがある。

ゲーム用語 (41-65)
- アーマー (Āmā)主に対戦格闘ゲームで、相手の攻撃を受けてもキャラクターがのけぞらなくなる特殊な状態。攻撃モーションを中断させられないため、相手の攻撃に割り込んで一方的にダメージを与えるといった強引な戦法が可能になる。「スーパーアーマー」とも呼ばれる。ただし、ダメージ自体は受けることが多い。
- 甘え (Amae)相手が反撃してこないだろう、この行動は見逃してくれるだろう、といった希望的観測に基づいた安易な行動。または、明らかにリスクが高いのにそれを実行してしまう油断したプレイを指す。上級者の対戦では、そうした一瞬の「甘え」が敗北に直結するため、常に緊張感が求められる。
- 暗転返し (Anten-gaeshi)対戦格闘ゲームにおいて、相手が超必殺技などを発動し、演出で画面が一瞬暗転したのを見てから、こちらも無敵時間のある超必殺技などを入力して反撃すること。相手の切り札を潰して反撃できるため非常に強力だが、入力の猶予時間が極めて短く、高い反射神経と正確な操作が要求される高等テクニック。
- 置き (Oki)対戦格闘ゲームで、相手がそこに移動してくる、あるいは技を出してくるであろうことを予測し、あらかじめ攻撃判定を「置いておく」ように技を出す戦法。相手の行動を先読みした、いわば「待ち」の戦術。牽制技や設置技などが「置き」に使われることが多く、相手にプレッシャーを与える効果がある。
- 完凸 (Kantotsu)ソーシャルゲーム(ソシャゲ)用語。「限界突破を完了した」の略。ガチャで同じキャラクターやアイテムを複数回引き当てることで、ステータスの上限を最大まで解放しきった状態を指す。多大な投資が必要になることが多く、そのキャラクターへの愛情や財力の証とされる。類義語に「宝具5」「4凸」など。
- カンスト (Kansuto)「カウンターストップ」の略語。RPGのレベルやステータス、シューティングゲームのスコアなどが、ゲームシステム上の上限値に到達し、それ以上上がらなくなった状態を指す。999,999点など、キリの良い数字で止まることが多い。やり込みの指標であり、プレイヤーにとって一つの到達点、目標となる。
- ケツワープ (Ketsu-wāpu)主に古い横スクロールアクションゲームなどで、画面外にフレームアウトした敵キャラクターが、画面の反対側(プレイヤーの背後、つまりお尻側)から突然ワープして出現する現象や仕様を指す俗称。予期せぬ方向からの攻撃に、多くのプレイヤーが理不尽な思いをさせられた。
- 香ばしい (Kōbashii)元はネットスラングだが、オンラインゲーム界隈では、チート(不正行為)を使っている疑いがあるプレイヤーや、言動が怪しいプレイヤーを指して使われる隠語。「胡散臭い」「きな臭い」といったニュアンスを持つ。直接的に「チーターだ」と断定するのを避けるための、やや遠回しな表現。
- 様式美 (Yōshikibi)対戦格闘ゲームなどで、実用性だけでなく、見た目にも美しく流れるような連続技(コンボ)や連携のこと。ダメージ効率だけを求めるのではなく、魅せるプレイを重視する価値観から生まれた言葉。見る者を感嘆させる芸術的なプレイは、プレイヤーの熟練度の高さを象徴する。
- 死体撃ち (Shitai-uchi)FPS(一人称視点シューティングゲーム)などの対戦ゲームで、既に倒して動かなくなった相手プレイヤーのキャラクター(死体)に対して、さらに銃撃を続ける行為。相手を侮辱し、煽るための非常に悪質なマナー違反とされており、多くのコミュニティで嫌悪されている。
- 人権 (Jinken)ソーシャルゲーム(ソシャゲ)界隈で使われる言葉。そのキャラクターやアイテムを持っていないと、高難易度コンテンツのクリアが著しく困難になったり、対人戦で全く歯が立たなかったりするほど、必須級の性能を持つものを指す。「人権キャラ」などと呼ばれる。ゲームを遊ぶ上での最低限の権利、という意味合い。
- スカ (Suka)攻撃が当たらず空振りしてしまうこと。「空かす(すかす)」が語源。特に格闘ゲームにおいて、確実に当たるはずの連続技の途中で攻撃が当たらず、相手に反撃のチャンスを与えてしまった際の「コンボをスカった」というような文脈で使われる。プレイヤーの操作ミスを指すことが多い。
- 尊師 (Sonshi)特定のゲーム、特にアーケードゲームのコミュニティにおいて、黎明期から業界を支え、卓越した技術と知識で他のプレイヤーから神のように崇められているレジェンド級のプレイヤーを指す、最大級の敬称。元々は宗教的な指導者を指す言葉だが、転じて深い尊敬の念を込めて使われる。
- 対あり (Tai-ari)「対戦ありがとうございました」の略。オンライン対戦ゲームで、試合の終了後にチャットなどで交わされる挨拶。マナーとして定着しており、勝敗にかかわらず相手への感謝と敬意を示す言葉として使われる。より丁寧に「対戦ありでした」と言うこともある。
- ナーフ (Nāfu)オンラインゲームなどで、アップデートによって特定のキャラクター、武器、戦術などの性能が下方修正(弱体化)されること。強すぎた要素のバランス調整が目的。アメリカの柔らかい素材でできたおもちゃの銃「NERF」が語源で、「威力がなくなる」というイメージから来ている。対義語は「バフ(強化)」。
- ノックバック (Nokku-bakku)攻撃を受けた際に、キャラクターが後ろに吹き飛ばされたり、後ずさりしたりする反応のこと。ノックバックが大きいと、敵との距離が離れてしまい、連続攻撃が途切れる原因になる。逆に、これを利用して相手をステージの端(壁際)に追い詰める戦術も存在する。
- バフ/デバフ (Bafu/Debafu)RPGやオンラインゲームで、キャラクターの能力値を一時的に上昇させる効果(ステータス強化)を「バフ」、逆に低下させる効果(ステータス弱体化)を「デバフ」と呼ぶ。味方にバフをかけて有利にし、敵にデバフをかけて不利にすることが、多くのゲームで戦略の基本となる。
- ピヨる (Piyoru)短時間に連続で多くのダメージを受けるなどして、キャラクターが気絶(スタン)し、一定時間行動不能になる状態を指す。頭上にヒヨコや星が回るエフェクトで表現されることが多かったため、この名が付いた。ピヨっている間は一方的に攻撃されるため、非常に危険な状態。
- リセマラ (Risemara)「リセットマラソン」の略。主にソーシャルゲームで、ゲーム開始時に引ける無料ガチャで、目当ての強力なレアキャラクターが出るまで、アプリのインストールとアンインストール(リセット)を何度も繰り返す行為。序盤を有利に進めるための、もはや定番となった儀式の一つ。
- レベリング (Reberingu)キャラクターのレベル(Level)を上げる(ing)ための行為。経験値を獲得するために、効率の良い狩場でひたすら敵を倒し続けるなど、地道な作業を指す。単に「レベル上げ」と言うよりも、よりシステム的な作業というニュアンスが強い。MMORPGなどで特に重要な要素。
- エンカウント (Enkaunto)RPG(ロールプレイングゲーム)で、フィールドやダンジョンを移動中に敵モンスターと遭遇し、戦闘に突入すること。「エンカウント率」は敵との遭遇しやすさの指標。敵が見えない状態でランダムに発生する「ランダムエンカウント」と、敵の姿が見えていて接触すると戦闘になる「シンボルエンカウント」がある。
- 古参 (Kosan)あるオンラインゲームやコミュニティに、サービス開始初期や黎明期から参加している古株のプレイヤーのこと。ゲームの仕様や歴史に詳しく、尊敬される存在である一方、新規プレイヤーに対して排他的な態度をとる「古参アピール」をする者は煙たがられることもある。
- TA (Tī Ē)「タイムアタック」の略。ゲームのクリアタイムや、特定の区間をいかに速く駆け抜けられるかを競う遊び方、またはその記録。コンマ1秒を削るために、最適化されたルートや操作技術を突き詰めていく、非常にストイックなやり込みプレイの一種。RTA(リアルタイムアタック)もこれに含まれる。
- ガチャ (Gacha)カプセルトイ(ガチャガチャ)から着想を得た、ランダム型アイテム提供方式。ゲーム内通貨や課金によって、キャラクターやアイテムなどを確率に基づいてランダムで入手するシステム。射幸心を煽るとして問題視される側面もあるが、多くのソーシャルゲームで主要な収益モデルとなっている。
- RMT (Āru Emu Tī)「リアルマネートレード」の略。ゲーム内の通貨やアイテム、アカウントなどを、現実世界の法定通貨(リアルマネー)で売買する行為。多くのオンラインゲームでは利用規約で明確に禁止されており、アカウント停止などの厳しい処罰の対象となる不正行為である。

アイドル・ファンカルチャー用語 (66-90)
- 赤飯 (Sekihan)文字通り、お祝いの席で食べられる「赤飯」。自分の応援する推し(アイドル、キャラクター等)に、メディア露出の決定やライブの成功、人気投票での一位獲得など、非常に喜ばしい出来事があった際に、「今夜はお祝いに赤飯を炊かなきゃ!」というように、ファンが自らの喜びを最大限に表現する言葉。
- イキリ骨太郎 (Ikiri Hone Tarō)ファンになったばかりの新参者にもかかわらず、まるで長年のファンのように知識や経験をひけらかし、偉そうに振る舞う(イキる)人を揶揄するネットスラング。匿名掲示板の書き込みが元ネタとされる。周りからは「痛い」存在として冷ややかに見られていることが多い。
- TO (Tī Ō)「トップオタク」の略。特定のアイドルやグループのファンの中で、最も多くの時間、お金、情熱を注ぎ込み、ファンコミュニティ内で最も影響力があるとされる人物を指す。握手会などのイベントに誰よりも多く参加し、その存在はアイドル本人や運営側にも認知されていることが多い。
- 推し被り (Oshikaburi)自分がいちばん応援しているイチオシのメンバー(推し)が、他のファンと偶然同じ(被っている)状態。ファン同士の交流のきっかけになる一方、「同担拒否」(後述)の思想を持つファンにとっては、嫉妬やライバル心の対象となり、トラブルの原因になることもある。
- オリキ (Oriki)「お気に入り」と「力(リキ)を入れる」を組み合わせた言葉。特定のアイドルに集中的に時間やお金を注ぎ込み、運営や他のファンに自分の存在を認めさせようとする、熱心すぎるファンのこと。時に私的な繋がりを求めたり、他のファンを出し抜こうとしたりする、やや否定的なニュアンスで使われる。
- 鍵開け/鍵閉め (Kagi-ake/Kagi-shime)握手会などの個別イベントで、あるメンバーのレーンにその日一番最初の客として入ること(鍵開け)、または一番最後の客として入ること(鍵閉め)。特に「鍵閉め」は、その日最後の挨拶を交わせる可能性があるため、ファンにとっては特別な価値を持つ行為とされる。
- ガチ恋 (Gachi-koi)アイドルや二次元のキャラクターに対して、ファンとしての憧れを超え、本気(ガチ)で恋愛感情を抱いてしまうこと。疑似恋愛を楽しむのではなく、現実の恋愛対象として見ているため、相手の熱愛報道などが出ると、ファンを辞めてしまう(担降りする)ケースも少なくない。
- 枯れる (Kareru)応援していたアイドル(推し)がグループを卒業したり、芸能界を引退したりして、応援する対象を失ってしまった状態を指す。また、熱心に通っていた現場への情熱が冷めてしまった状態を指すこともある。植物が枯れる様子に、ファンの心の喪失感を重ね合わせた表現。
- ケチャ (Kecha)ライブやコンサートで、バラード曲のサビなど、楽曲が一番盛り上がる感動的な場面で、ファンがステージ上のアイドルに向かって両手をゆっくりと差し出す行為。インドネシアのケチャダンスが由来とされる。会場の一体感を生み出す代表的なファンアクションの一つ。
- 接触 (Sesshoku)握手会、サイン会、チェキ会(ツーショット撮影会)など、ファンがアイドルと直接的に触れ合ったり、至近距離で会話したりできるイベントの総称。「接触イベント」とも呼ばれる。CDなどの商品に特典として参加券が付与されることが多く、売上を支える重要な要素となっている。
- 積む (Tsumu)握手券やイベント参加券、投票券などを複数枚手に入れる目的で、同じCDや商品を大量に購入する行為。物理的にCDが山積みになる様子からこう呼ばれる。推しと会う機会を増やしたり、人気投票で上位にランクインさせたりするための、ファンによる経済的な貢献活動。
- 同担拒否 (Dōtan-kyohi)自分と同じ担当(=推し)を応援している他のファン(=同担)を、仲間として受け入れたくない、関わりたくないと考えるスタンスのこと。推しへの独占欲が強いファンに見られ、「同担=ライバル」と見なす。SNSのプロフィールなどで「同担拒否」を公言している人もいる。
- 認知 (Ninchi)イベントに何度も通うなどして、自分の顔と名前を推しのアイドルに覚えてもらうこと。ファンにとっては最高の栄誉の一つとされる。「○○さん、また来てくれたんですね」といった一言をもらうために、多くのファンが努力を重ねている。ファン活動の大きなモチベーションとなる。
- 剥がし (Hagashi)握手会で、規定の時間が来たファンを、アイドルの前から引き離す役割のスタッフのこと。スムーズなイベント進行のために不可欠な存在だが、ファンにとっては会話の途中で強制的に終了させられるため、恨めしい存在でもある。その引き離す力の強弱が話題になることもある。
- ピンチケ (Pinchike)ライブやイベントにおけるマナーが悪い若年のファン(特に中高生)を指す蔑称。かつて一部のイベントで学生向けに配布されていた「ピンク色のチケット」で入場する者が多かったことに由来する。騒ぎたいだけで、アーティストへの敬意が薄い層、という否定的なニュアンスで使われる。
- マウント (Maunto)他のファンに対して、自分の方がファン歴が長い(古参)、イベントに多く参加している、推しから認知されている、などといった点で優位に立っているとアピールし、精神的に優越感に浸ろうとする行為。「マウンティング」とも言う。ファン同士の人間関係を悪化させる原因の一つ。
- レス (Resu)「レスポンス(response)」の略。コンサート中に、ステージ上のアイドルから、自分個人に向けてウインクや指差し、手を振るといった反応をもらうこと。数多くの観客の中から自分を見つけてくれた、という感覚が、ファンにとっては何物にも代えがたい喜びとなる。
- リアコ (Riako)「リアルに恋している」の略語。アイドルやキャラクターを、手の届かない憧れの存在としてではなく、現実世界で本気で恋愛対象として見ているファン、またその状態を指す。「ガチ恋」とほぼ同義で使われるが、より口語的で若い世代が使う傾向がある。
- 箱推し (Hako-oshi)アイドルグループにおいて、特定の誰か一人を応援する(単推し)のではなく、グループ全体、メンバー全員を応援するスタイルのこと。グループという「箱」そのものが好き、というニュアンス。メンバー同士の和気あいあいとした雰囲気や、グループとして作り上げるパフォーマンスを愛でるファン。
- 厄介 (Yakkai)ライブ会場で奇声を発したり、過度に激しい動きで周囲に迷惑をかけたり、独自のルールを強要したりするなど、イベントのルールやマナーを守らない迷惑なファンの総称。「厄介オタク」とも言う。他のファンの楽しみを奪い、時にはイベントが中断・中止になる原因ともなる。
- 在宅 (Zaitaku)コンサートや握手会などの「現場」には行かず、自宅でCDやDVD、テレビ番組などを楽しむことを主とするファンのこと。対義語は、現場に足繁く通う「現場派」。金銭的、時間的、地理的な制約から在宅になるケースが多い。ネットでの情報収集や応援に熱心な人もいる。
- 単推し (Tan-oshi)アイドルグループの中で、特定のメンバー一人だけを集中して応援するスタイルのこと。そのメンバーのグッズだけを買い、そのメンバーが出演するイベントにだけ参加する、といった行動をとる。「DD(誰でも大好き)」の対義語として使われる。
- DD (Dī Dī)「誰でも大好き」の頭文字を取った略語。特定の推し一人に絞らず、複数のアイドルやグループを掛け持ちで応援しているファンのこと。元々は節操がないと揶揄するニュアンスもあったが、現在では単純に博愛主義的なファンを指す言葉として広く使われている。
- 沸く (Waku)ライブなどで、大声でコール(掛け声)を入れたり、ジャンプしたり、激しく体を動かす(振りコピなど)パフォーマンスをしたりして、極度に盛り上がること。一般的な盛り上がりよりも、さらにエネルギッシュで激しい応援スタイルを指す。周囲への配慮を欠くと「厄介」と見なされることもある。
- 接触厨 (Sesshoku-chū)アイドルの歌やダンスといったパフォーマンスにはあまり興味がなく、握手会やチェキ会などの「接触」イベントにばかり熱心に参加するファンを、やや蔑んで呼ぶ言葉。「〜厨」は、ある物事に熱中しすぎる人を指すネットスラング。楽曲よりもアイドルとの会話や触れ合いを至上と考える層。

その他・ニッチな用語 (91-100)
- アクスタ (Akusuta)「アクリルスタンド」の略語。キャラクターのイラストやアイドルの写真を、透明なアクリル板に印刷し、人型にカットしたもの。台座に立てて飾ることができる。コレクション性が高く、カフェや旅行先などに持参して風景と一緒に撮影する(「ぬい撮り」ならぬ「アクスタ撮り」)など、多様な楽しみ方が生まれている。
- 痛車 (Itasha)自動車の車体に、アニメやゲームのキャラクターのイラストやロゴなどを、ステッカーや塗装で大きく装飾したカスタムカー。「見ていて痛々しい」と「イタリア車」を掛け合わせた俗語。所有者のキャラクターへの深い愛情表現だが、一般人からは奇異の目で見られることも多い、オタク文化の象徴の一つ。
- 岩盤 (Ganban)長年にわたって人気が衰えず、商業的に大きな成功を収め、非常に強固で大規模なファン層を持つジャンルや作品群を指す。まるで一枚岩の地盤のように、市場での地位が揺るがないことからこう呼ばれる。流行り廃りに左右されない、オタクコンテンツ市場における基盤のような存在。
- 解釈違い (Kaishaku-chigai)公式から発表された新しいストーリー展開や設定、あるいはファンによる二次創作の表現が、自分が抱いていたキャラクター像や関係性のイメージ(解釈)と異なっている状態。時に深刻な精神的ダメージを伴い、ファン活動のモチベーション低下や、時にはジャンルからの離脱につながることもある。
- 聖地巡礼 (Seichi Junrei)アニメ、漫画、ゲームなどの作品の舞台となった実在の土地や建物を、ファンが「聖地」として実際に訪れ、作品の世界に思いを馳せる行為。近年では、地域振興(町おこし)の一環として、自治体が聖地巡礼を歓迎し、ファン向けのマップ作成やグッズ販売を行うケースも増えている。
- 膳 (Zen)推しへの愛情や尊さを表現する際に使われる、一部の界隈における独特の単位。推しの素晴らしい活躍や供給(公式からの新規情報など)に接した際に、「今日の推しは尊すぎてご飯が三膳食べられる」というように、感謝と興奮の度合いを示す一種のバロメーターとして機能する。
- 宅録 (Takuroku)「自宅録音」の略。アマチュアのファンが、自宅の録音機材(PCやマイクなど)を使って、好きなキャラクターの声真似をしたり、歌を歌ったり(「歌ってみた」)、オリジナルのボイスドラマを制作したりして、インターネット上で公開すること。個人が手軽に創作活動を行えるようになった現代ならではの文化。
- 沼 (Numa)一度ハマると自力では抜け出せないほど、特定のジャンルやキャラクター、カップリングに夢中になってしまう状態の比喩表現。「(作品名)の沼に落ちた」「ここは深い沼だ」のように使う。底なし沼のように、次々と関連グッズやコンテンツにお金や時間を費やしてしまう、抗いがたい魅力を指す。
- nmmn (Namamono)実在する人物(アイドル、俳優、芸人、スポーツ選手など)を題材にした、ファンによる二次創作(小説やイラストなど)を指す隠語。「生もの」と読む。非常にデリケートなジャンルであるため、ご本人や一般の人の目に触れないよう、検索避けのために伏せ字として使われる。
- 界隈 (Kaiwai)同じジャンル、同じグループ、同じキャラクターなどを応援している、特定のファン層が集まったコミュニティやその周辺を指す言葉。「○○(ジャンル名)界隈では常識」「あの人はこの界隈の有名人だ」のように使う。オタクたちが帰属意識を持つ、それぞれのコミュニティのテリトリーを示す。
まとめ
いかがでしたか?
今回ご紹介したのは、広大なオタク用語の海のほんの一滴にすぎません。これらの言葉は、各ジャンルを愛する人々が、その熱量と探究心をもって育んできた文化そのものです。
もし半分以上わかったなら、あなたは相当な”通”。一つもわからなくても、落ち込む必要はありません。これが、あなたがこれから足を踏み入れるかもしれない、新しい「沼」の入り口なのですから。
さて、あなたはいくつの言葉を知っていましたか?コメントでぜひ教えてくださいね!
オタク文化における「大手」は、ジャンルによって多岐にわたります。特定の単一企業が全体を支配しているわけではなく、各分野で影響力の強い企業群が存在します。以下に、主要なジャンルごとの大手企業・団体をまとめました。
1. アニメーション
アニメ業界は、実際に制作を行う「制作会社」と、企画や出資、商品化などを手掛ける「製作会社(プロデュース・IPホルダー)」に分かれます。
- 株式会社アニプレックス (Aniplex Inc.) ソニー・ミュージックエンタテインメント傘下で、『鬼滅の刃』や『Fate』シリーズなど数多くの大ヒット作を手掛ける企画・製作会社。音楽やゲーム、イベントなど多角的な展開(メディアミックス)に非常に強い影響力を持ちます。
- 東映アニメーション株式会社 (Toei Animation Co., Ltd.) 『ドラゴンボール』、『ONE PIECE』、『プリキュア』シリーズなど、国民的・世界的な知名度を誇る作品を多数制作する老舗にして最大手のアニメ制作会社です。
- 株式会社KADOKAWA (KADOKAWA CORPORATION) 出版社でありながら、アニメの企画・製作(製作委員会への出資)にも深く関与しています。『Re:ゼロから始める異世界生活』など、自社のライトノベルや漫画の強力なアニメ化展開が特徴です。
- 株式会社MAPPA 『呪術廻戦』や『進撃の巨人 The Final Season』など、近年特にハイクオリティな映像で話題作を次々と生み出している、非常に勢いのあるアニメ制作会社です。
2. 出版(漫画・ライトノベル)
日本のオタク文化の根幹である漫画やライトノベルは、以下の大手出版社が市場を牽引しています。
- 株式会社集英社 (SHUEISHA Inc.) 『週刊少年ジャンプ』で知られ、『ONE PIECE』、『NARUTO -ナルト-』、『呪術廻戦』など数々の大ヒット漫画を世に送り出しています。
- 株式会社講談社 (Kodansha, Ltd.) 『週刊少年マガジン』や『月刊アフタヌーン』などを発行し、『進撃の巨人』や『東京卍リベンジャーズ』など幅広いジャンルのヒット作を抱えています。
- 株式会社小学館 (Shogakukan Inc.) 『週刊少年サンデー』や『コロコロコミック』などを発行し、『名探偵コナン』や『ドラえもん』など、子供から大人まで楽しめる作品に強みがあります。
3. ゲーム
家庭用ゲーム機からスマートフォンアプリまで、日本のゲーム業界は世界的に大きな影響力を持っています。
- 任天堂株式会社 (Nintendo Co., Ltd.) 「スーパーマリオ」や「ポケットモンスター」、「ゼルダの伝説」シリーズなどを擁し、Nintendo Switchで家庭用ゲーム市場をリードする世界的な企業です。
- 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント (Sony Interactive Entertainment Inc.) 「PlayStation」プラットフォームを展開し、高品質なゲームソフトで世界中のゲームファンを魅了しています。
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント (Bandai Namco Entertainment Inc.) 『機動戦士ガンダム』シリーズや「テイルズ オブ」シリーズ、『ELDEN RING』など、自社IP・他社IP問わず多様なジャンルのゲームを開発・販売しています。
- 株式会社Cygames (Cygames, Inc.) 『グランブルーファンタジー』や『ウマ娘 プリティーダービー』など、スマートフォン向けゲームで社会現象を巻き起こした大手です。
4. グッズ・ホビー
フィギュアやキャラクターグッズ、同人誌などを扱う小売・製造業もオタク文化の重要な柱です。
- 株式会社アニメイト (animate Ltd.) アニメ・漫画・ゲーム関連のキャラクターグッズを専門に扱う国内最大手の小売店。全国に店舗網を持ち、オタク文化のインフラ的存在です。
- 株式会社グッドスマイルカンパニー (GOOD SMILE COMPANY, Inc.) デフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズで世界的に有名なフィギュアメーカーの最大手。企画力と品質の高さでファンから絶大な支持を得ています。
- 株式会社虎の穴 (Toranoana Inc.) 同人誌の委託販売を中心とした専門店の大手。クリエイターとファンを繋ぐ重要なプラットフォームです。
5. アイドル・イベント
アイドル文化や大規模イベントも、現在のオタク文化を語る上で欠かせません。
- 株式会社STARTO ENTERTAINMENT 長年にわたり男性アイドル市場を牽引してきた、日本のエンターテインメント業界を代表する大手芸能事務所です。
- 坂道シリーズ(乃木坂46合同会社など) 「乃木坂46」「櫻坂46」「日向坂46」などを擁し、現在の女性アイドルシーンを代表する一大勢力です。
- コミックマーケット準備会 世界最大の同人誌即売会「コミックマーケット(コミケ)」を主催する団体。アマチュアクリエイターの発表の場として、半世紀近くにわたり文化の根底を支えています。
これらの企業・団体は、それぞれが専門分野で強固な地盤を築き、相互に関わり合いながら巨大なオタク文化のエコシステムを形成しています。